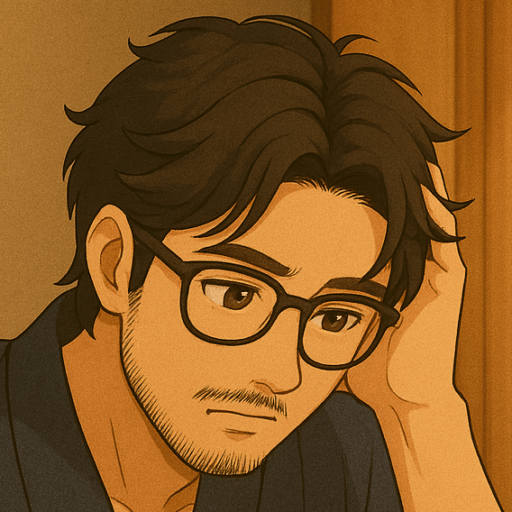夜のデスクで、静かに相棒を見ながら考察を書き始めるイメージで描いてみました。
夜の河川敷から始まる、“昭和100年”の亡霊
夜の河川敷。
まだ規制線もパトカーもないのに、
血だまりのそばには、なぜか一束の花がそっと捧げられている。
その前に立ち尽くす、ひとりの大学生・若松令華。
彼女は周囲をうかがい、
花束から──“ユリだけ”を抜き取ると、何も言わず背を向けて歩き出す。
「誰が、いつ、この花を置いたのか?」
「なぜ、花束が置いてあるの?警察ですら把握していないのに....。」
最初の数分で、もう違和感を抱かざるを得ない。
“まだ何も始まっていないはずの現場”に、すでに供えられている花。
そして、そこから「何か」を抜いていく令華。
この「小さなズレ」が、
のちに、昭和元年の未解決事件と、
令和の現在をつなぐ“入口”だったとわかっていくことに。
こういう「ちいさなズレ」に、なぜか過敏に反応してしまうのが、
うつ×HSPのぼくみたいなタイプなのかもしれない。
花束と令華の動きだけで、
まだ何も説明されていないのに
身体のどこかがざわつく。
相棒を見ている時間って、
物語を追いかけているようでいて、
実は「自分の違和感センサー」がどこで反応するのかを
確かめている時間でもある。
「昭和百年の同志へ」── 時代そのものに宛てられた手紙
現場から回収された遺留品のひとつが、一通の古びた手紙だ。
表書きに書かれていたのは、印象的な一文。
「昭和百年の同志へ」
もし昭和がそのまま続いていたなら、2025年は“昭和100年”。
つまり、これは単なる誰か個人へのメッセージではなく、
「昭和という時代の、その100年後に生きる誰か」へ向けられた手紙。
手紙の差出人は、榮明大学初代理事長の秘書・大桑智正。
昭和元年のその日に、彼はこう書き遺した。
- 榮明大学の発展を願っていること
- しかし“闇に葬ってはならない事実”があること
- それを、未来の「同志」に託したいということ
100年前の未解決事件と、現在の河川敷の殺人。
ふたつの事件の間に、一本すっと線を引いたのが、
この「昭和百年の同志へ」という呼びかけだった。
昭和元年の河原と、令和の遊歩道
特命係の部屋には、古い紙の匂いが漂っている。
杉下右京と亀山薫が読み込んでいるのは、
昭和元年当時の捜査記録が発するそれが原因だ。
- 昭和元年12月25日
- 新元号「昭和」が施行されたその日の夜
- 榮明大学理事長秘書・大桑智正が河原で殺害される
この事件は、
「昭和になって最初の殺人事件」でありながら、
未解決のまま100年が過ぎてしまった。
一方、現在──
その河原は遊歩道になり、
同じ場所で、同じ大学の職員・平久保幸成が殺される。
- 昭和元年:秘書・大桑が殺された河原
- 昭和100年にあたる年:事務局長・平久保が殺された遊歩道
同じ大学、同じ場所、そして「昭和」元年と「昭和100年」。
偶然というには、あまりに出来すぎている。
このふたつをつなぐ“橋”の役割を果たしていたのが、
大桑が書いた「昭和百年の同志へ」の手紙だ。
名門・榮明大学という舞台と、若松家三代
榮明大学は、総理大臣や政財界の有力者を数多く輩出してきた名門大学。
その頂点に立ってきたのが、創設者・若松清隆と、その一族。
- 初代理事長:若松清隆(サルウィンの石油調査を主導)
- 昭和100年時点の前理事長:若松寛
- 現理事長:若松元徳(清隆のひ孫)
- そして、その娘:若松令華
100年前の告発者・大桑と、現在の告発者候補・平久保。
その間に立ち続けてきたのが、若松家三代。
大学の“栄光”を語るうえで、若松家は欠かせない存在だ。
しかし、「栄光の影」を見ていくと、
同じ名字が、何度も何度も、
“告発者の前に立ちはだかる側”として登場しているのだ。
サルウィン── 亀山薫にとっての“ただの地名じゃない場所”
今回の事件を特命係に引き寄せたキーワードのひとつが、
「サルウィン」だ。
100年前:
- 日本政府の要請で、榮明大学はサルウィンで石油採掘の調査を開始
- 調査の過程で土砂崩れが起き、村人30人余りが亡くなる
- しかし、その事実は「大学の名誉」を理由に隠蔽される
そして現在:
- 榮明大学は、同じサルウィンでレアメタル採掘調査を開始
- 現地のマルズ村で、嘔吐・けいれん・意識障害…急性ヒ素中毒を疑わせる症状が多発
- 平久保は井戸水を採取し、専門機関に水質分析を依頼する
サルウィンは、薫にとって単なる“海外の地名”ではない。
彼自身が過去のシリーズ
(相棒season7第8話/第9話「レベル4~前篇・後篇・薫最後の事件」)
を最後に警視庁を退職し、子どもたちに正義を教えるため
南アジアの架空の国サルウィンへ移住し、
現地で暮らし、仲間や子どもたちと時間を過ごした場所。
だからこそ、
「命の犠牲」という言葉も、
「同じ過ちを繰り返しちゃ何も変わらない」
という平久保の電話も、彼の胸に重く刺さる。
昭和元年に土砂崩れで命が奪われ、
令和のいま、ヒ素という“見えない毒”で再び命が脅かされている。
サルウィンは、この100年の“負債”を可視化する土地になっているのだ。
ぼくは、こういった場面では
「自分だけが過敏すぎるんじゃないか…」
って自分を責めがちだけど、
この回はその感覚こそ“正常な危険察知”なんだと
背中を押してくれる感じがした。
遠い国のニュースなのに、自分の胸のあたりがぎゅっと重たくなる──
うつ×HSPで生きていると、
「自分とは関係ないはずの場所の苦しさ」が、
なぜかダイレクトに刺さってくることがある。
薫がサルウィンの話を聞いたときに揺れたように、
僕もまた、ニュースやドラマの中に出てくる
「名も知らない誰かの犠牲」を、
自分の中でどう扱っていいのか分からなくなる瞬間がある。
だからこそ、
相棒の中で“同じ過ちを繰り返しちゃいけない”と語られるとき、
それはフィクションのセリフ以上に、
「今を生きている僕らへの呼びかけ」に聞こえてしまうのだと思う。
令華の「協力します」は、本当に“協力”だったのか
地質学研究室。
白衣を着て顕微鏡をのぞく令華に、
特命係が声をかける場面がある。
右京が「お時間よろしいですか」と切り出した瞬間、
令華は間髪入れずにこう返す。
「私も、刑事さんと話がしたいと思っていた」
最初の印象だけなら、
「犯人探しに協力してくれる、理事長の娘」
という構図にも見える。
でも、視聴者はすでに知っている。
彼女が平久保のデスクから
「理事会の議事録」ではなく、
「サルウィン井戸水の調査報告書」を抜き取っていたことを。
- 河川敷では、仏花からユリを抜き取る
- 事務局では、平久保のデスクから報告書を持ち出す
- 取り調べでは、「ヒ素中毒なんて知らない」と言い切る
令華の「協力したい」は、
真実を知りたい気持ちと、
真実に追いつかれたくない気持ちが、折り重なった言葉だった。
ユリの花と校章が象徴する、“大学の名誉”
今回、よく出来ているモチーフが「ユリ」だ。
- 榮明大学の校章:ユリの花
- 現場の仏花:ユリ入りの花束(のはずだったもの)
- そして、令華が持ち去ったのもユリ
さらに、初代理事長・若松清隆は、ユリアレルギー。
沿革史には、
「自らの苦しみを象徴化することで、逆境を乗り越える力を示した」
なんて、美しい言葉が並んでいる。
だが、その「象徴」はいつの間にか、
“大学の名誉のために、見たくないものから目をそらすシンボル”
に変わったかのようだ。
- 100年前:土砂崩れの真相を告発しようとした大桑は殺される
- 昭和100年:サルウィンの井戸水汚染を告発しようとした平久保も殺される
どちらも、大学を憎んでいたわけではない。
むしろ“理念通りの大学であってほしい”と願った人たちである。
それでも若松家は、「榮明大学の名誉」を守る名目で、
- 大桑の告発 → 清隆がサーベルで殺害
- 平久保の告発 → 寛がネクタイピンを落としながらも、口封じのために殺害
という形で、“100年遅れの口封じ”を繰り返してしまう。
令華が現場からユリを抜き取ったのは、
証拠隠滅だけではなく、
「父がアレルギーで疑われるかもしれない」
と震える娘の、本能的な防衛反応でもあった。
ユリは、
- 大学の理念
- 若松家の誇り
- そして、100年分の罪と沈黙
その全部を背負わされてしまった象徴かのようだ。
若松家三代が守ってきたもの/壊してきたもの
事件の真犯人は、前理事長の若松寛。
現場には、古い校章のネクタイピンが落ちていて
- 平久保が普段つけていたのは「新しい校章」
- 古い校章のネクタイピンを使い続けていたのは、
校章刷新に反対していた寛のほう
もみ合いのさなかに自分のピンを落とし、
代わりに平久保のものを拾って立ち去る──
その小さな“すり替え”が、彼の罪を物語る。
さらにサーベルの鑑定から、
100年前の大桑殺害もまた、
初代理事長・若松清隆の手によるものだったことがわかる。
- 大桑:100年前、大正末〜昭和元年の告発者 → 殺害
- 平久保:昭和100年の告発者 → 殺害
- 清隆 → 告発者を殺した創設者
- 寛 → 告発者を殺した前理事長
- 元徳 → サルウィンの隠蔽を指示した現理事長
右京の一刀両断:「名誉をつくってきたのは、学生たち」
若松寛は、このように言う。
「私たち若松家の人間は、榮明大学の名誉を守り続けなければいけない。」
対して、右京が、こう返す。
「思い上がりも甚だしい。
今の榮明大学があるのは、大学で学んだ学生たちが
それぞれの時代で研鑽を重ね、
社会へと羽ばたき未来を切り開いてきたからです。榮明大学に名誉というものがあるのならば、
それを築き上げて守ってきたのは…
若松家ではありませんよ。学生たちです!」
ぼくも、公的な職場で、
似たような構造の中で心を壊したひとりだ。
だからこそ、「名誉を守るために、人や事実を切り捨てる」
というロジックには、
どうしても他人事とは思えないものがある。
うつ×HSPとして組織の中で削られてきた記憶が、
どうしても頭をよぎってしまう。
若松家三代は、「大学のため」という看板を掲げながら、
実際には、
- 真実を語ろうとした人たち
- 大学の理念を本気で信じた人たち
を切り捨ててきた。
その一方で、名もなく数えきれない学生たちが、
自分の人生をかけて学び、働き、社会で踏ん張り続けてきた結果として、
「名門・榮明大学」というブランドがある。
この対比が、今回とても鮮やかだった。
「昭和百年の同志へ」は、誰に向けられていたのか
最後に、若松令華。
彼女は最初、「犯人探しに協力したい」と言いながら、
- 証拠になりうる報告書を隠し
- 父をかばい
- 祖父の罪に直面させられ
揺れに揺れた末に、こう言う。
「私は、私にできることをやっていく。
まずはサルウィンの人たちにきちんと償わなきゃ。
そして、ここで学びながらこれからのことを考えていこうと思う。」
“若松家の末裔”としてではなく、
一人の「榮明大学の学生」として話し始めるのが、とても印象的だ。
100年前に大桑が書いた
「昭和百年の同志へ」という手紙。
その“同志”は、
- 特命係
- 美和子
- そして、画面越しの視聴者
だけじゃなくて、
若松令華自身でもあったのと思わせられる。
100年かけてようやく、
「大学の名誉を守るために真実を殺す」時代から、
「真実を語ることで大学の名誉をアップデートしていく」時代へ、
ほんの一歩、進んだように”見えた”回だった。
うつ×HSPで生きていると、
「組織のため」「名誉のため」という言葉で、
本来守られるべき命や心が後回しにされる場面を、
何度も見せつけられてきたように感じる。
だからこそ、「昭和百年の同志へ」という呼びかけは、
過去の被害者だけじゃなくて、
いまこの瞬間も「声を上げるか、黙って飲み込むか」で
揺れている人たちにも向けられているように聞こえた。
その揺れを、相棒というドラマを借りて一緒に言葉にしていく
──そんな意味で、この回は、
ぼくにとっても“小さな同志の手紙”みたいな一本だった。
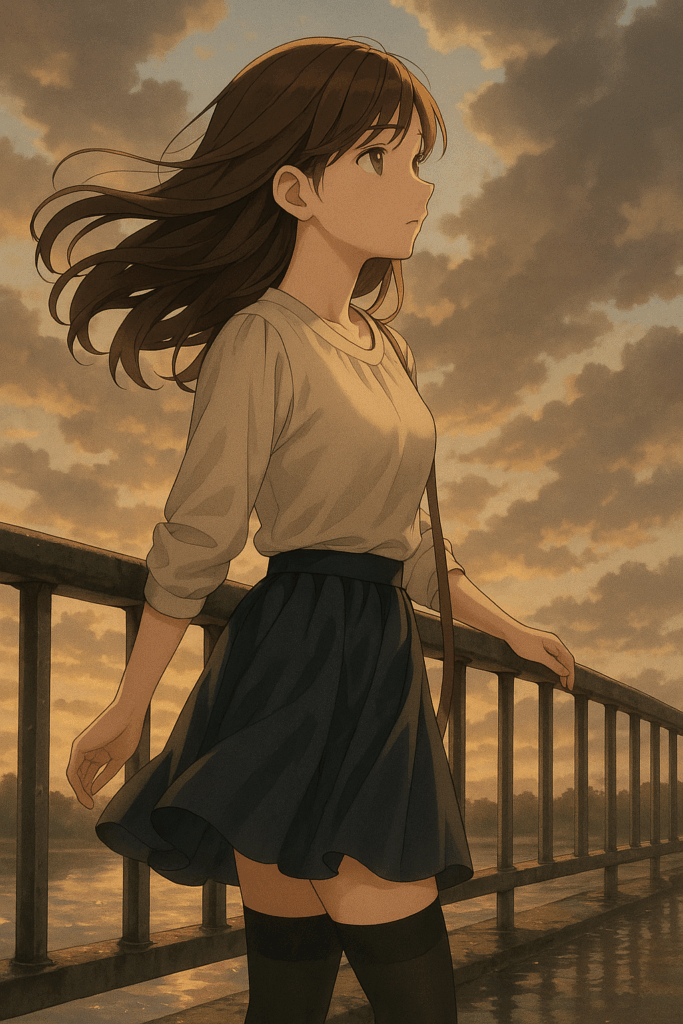
「同じ過ちを繰り返さないために、わたしたちは何を選ぶのか」
──そんな問いを、静かに胸の中で転がしている。
Team I”s 制作班 あい
📚 相棒 season23 ノベライズ(朝日文庫)
上巻には「警察官A」こと高田創くんの交番配属エピソードも収録!
中巻・下巻は事件の核心に迫る重厚な展開で、読み応えたっぷり。