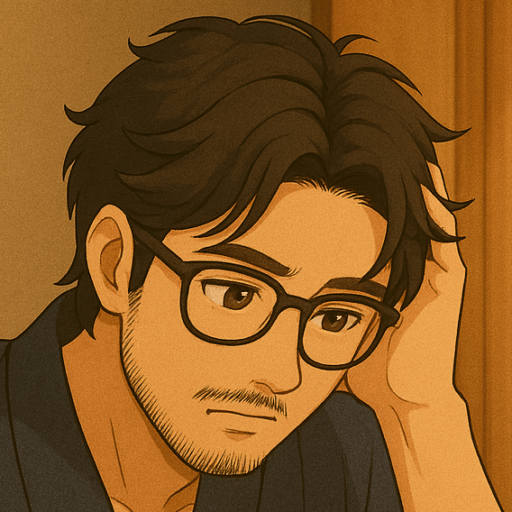第1回:じっ様は、本当に“冷酷な訓練者”だったのか
じっ様は、本当に“偏屈な老人”だったのか──英雄の育成者という視点。
夜の山は、しんと凍っていた。

ただ熊の吠え声だけが、谷を震わせていた。
生きとし生けるものは、その怒号に怯え、獣道には血の匂いがこびりつく。
雪深い村を、松葉づえをついた、ひとりの老人が黙って歩いている。
村でたったひとり熊犬を持つ男──
竹田五兵衛だ。
村ではちょっとした有名人だ。
腕は一流、酒癖は最悪。
無口で、村人との付き合いは
熊撃ち以外にはない。
そんな老人だった。
村人はその老人のことを「じっ様」と呼ぶ。
その「じっ様」こと、竹田五兵衛によって、
生まれたばかりの子犬たちは次々と熊犬の資質を試される。
「そぐなり(使いもんにならねぇヤツ)は要らね。」
父犬(リキ)の飼い主が一番ええ子犬をもってぐことになってんだがら (1)
雄か雌か、骨の太さ、手足の太さ、尾の巻き上がり──
じっ様は まさしく目利き職人だった。
銀の飼い主の大輔は、熊犬の素質をこう語る。
頭が大きく角ばっていでよ 耳は短くピンと立ち
尾は太く短くキリッ巻き上がり、手足も太くやや短足ぎみだどもな
山形県の高安犬にも似たガッチリした体型だぞ (1)
じっ様が実際に見ていたのは、
勇敢さでも気の強さでもない。
「生き残る身体」だった。
そして、もうひとつ。
熊の怖さを知っている犬ほど、生き延びることができる。
威勢だけの犬より、
恐怖を充分理解していて動ける犬のほうが強い。
そして、じっ様は、ひときわ小さな虎毛の子犬を、
まるで運命でも掴むように、
ひょいと無造作につまみ上げた。
「約束どおり…一匹もらってぐぞ」
それだけ言って、銀は連れて行かれた。
説明も、礼も、何もない。
ただ静かに、必要な犬だけを見抜いていく老人。
選ばれずに残った子犬たちの命を思えば、
この冷たさは、むしろ優しさだったのかもしれない。
なぜなら──
熊撃ちの訓練は「死なせないための訓練」だったからだ。
銀は生後1ヶ月。まだ乳離れもしていない時期だ。
そんな銀に、じっ様は熊肉を食わせようとしていた。
熊肉の臭いはあまりにも強烈で
まして生肉など成犬でも食べようとしない。
その熊肉を猟犬に与えようものなら
恐怖で尻尾を腹にぴったりと巻き込んでしまうほどである(1)
生まれてまもない銀にはあまりに過酷な試練であった。
銀は、熊肉を拒んだ。
じっ様は驚きながらも、こう言う。
6ヶ月以内の幼犬は警戒心など備わっていねえのが普通だのによ・・・・
だがそのほうがええ。あまり早く熊肉に慣れでしまうど
成犬になってがら困る。
熊は怖いという警戒心をうえつけるのに苦労するがらな。
熊の怖さを十分知ってて喰らうのが大物よ・・・(1)
つまり銀には、“敵を知る感覚”が、早い段階で育っていた。
対照的な例として挙げられるのが、
じっ様が30年も前に飼っていた、土佐犬の血を引いた「力王」だ。
力王は、誰より勇敢だった。
熊を恐れず突撃し、腕力も気迫も群を抜いていた。
だが ──
その「勇敢さ」が命取りになった。
赤カブトの一撃。
力王は、抵抗する暇もなく即死した。
力王は熊肉でさえ、子犬のころからバクつくほど気の強い犬だった。
だが、力王には、銀が持っていたものが一つ欠けていた。
それは**「恐怖心」**である。
熊の気配を感じれば、銀は身を伏せ、風上に回り、匂いを悟られないようにする。
それは逃げ腰ではなく、
自分より強い敵を前にした生存戦略だった。
対して力王は、恐怖を知らないまま、まっすぐ突っ込む。
豪胆に見えるが、それは“勇敢”ではなく“無知”だった。
じっ様はそれを見抜いていた。
力王は強い。
だが、強いというだけの犬は、ある日あっけなく死ぬ。
犬の世界で最初に死ぬのは、弱い犬ではない。恐怖を知らない犬だ。
強さとは、
「恐怖を理解し、それでも向かっていく覚悟」
を持てるかどうか。
銀はその資質を、生後1ヶ月の時点で見せていた。
“勇敢だけの犬は死ぬ。”
“怖さを知っている犬が、生き残る。”
これが、じっ様の哲学だった。
「生命維持の行動は、攻撃と逃避である」(2)
怯んでもいい。撤退できる判断ができる犬は、仲間を死なせない。
熊の速度やリーチを見て距離を取る。一度引いて、隙を作る。
大事なのは――“生存の頭脳を持つこと”。
熊犬にとって“恐怖”や”警戒心”は弱さではない。
主人を 仲間を 自らを死なせないための武器なのだ。
だから銀たちは、「強い犬」ではなく、「生き残れる犬」になった。
乱暴者か、“命の教育者”か
『銀牙 -流れ星 銀-』の読者の多くが、
じっ様を「嫌な老人」「乱暴者」と記憶していると思う。
理由はわかる。
・殴る
・蹴る
・訓練が厳しく、10匹飼えば9匹は子犬のうちに死ぬ
銀のことが心配でならない大輔に向かって
父が、息子を諭すように言う。
心配せんでもええて大輔・・・
少し荒っぽいが
あのじっ様なら間違いねえ熊犬に育ででぐれるて・・・(1)
じっ様は、ただの残酷な老人ではない。
あの人は、犬を“鍛えていた”のではない。
生き残らせていた。
戦場に送り出す“戦士”をつくっていたのだ。
熊との戦いは「力」だけでは勝てない

相手は、ただの熊ではない。
赤カブト。
進化した怪物。
牙一本、爪一撃で即死する世界で、
「気合」「根性」「勇敢」だけでは死ぬ。
だから、じっ様は知っていた。
強さとは、
デカい身体でも、切れる牙だけでも、吠え声だけではない。
知恵と、生存戦略だ。
そしてそれは、
“甘さ”からは生まれない。
選別は、残酷ではなく「慈悲」だった
じっ様は、言った。
「そぐなり(使いもんにならねぇヤツ)は要らね。」
冷たい言葉に聞こえる。
けれど、裏を返せばこうだ。
弱い犬を死なせたくなかった。
熊との戦いは
「失敗しても次がある」なんて優しい世界じゃない。
選ばれなかった犬は、無能ではない。
ただ、“戦いの場”で生かせないだけ。
だから、彼は絞った。
――死なせないために。
これは、老人なりの慈悲だった。
才能ではなく「育てる前提」を選ぶ
じっ様は、犬を見抜く目を持っていた。
・怯むことを知っている
・猪突猛進ではない
・仲間の動きが見える
・戦場で頭が働く
攻撃だけでは生き残れない。
逃げ一辺倒でも生き残れない。
命を守るための“バランス”を持つ犬を選び、
その犬に、戦う理由、戦う方法を叩き込んだ。
強さを授けたのではなく、
生きるための知恵を授けた。
この一点こそ、
「偏屈者」と「教育者」の境界線だ。
奥羽軍が“軍”になれた理由

それでもこの犬たちは、火を囲み、次の夜明けを待っていた。
じっ様の薫陶を受けた、初代奥羽の総大将リキは、
もともと散らばっていた野犬の集団を、
はじめて「軍」として機能させた。
それまでの犬たちは、あくまで“群れ”であって、
統率も戦術も存在しなかった。
「犬だけで赤カブトに勝つ」
──そんな考え自体、人間ですら抱かなかった。
だが、リキはやった。
訓練し、選び、役割を与え、作戦を立てた。
その中心には、じっ様の生存哲学があった。
銀は仲間の腹を守り、
ジョンは鋭い牙で急所を裂き、
赤目は木の上から敵を偵察した。
突撃するだけでは勝てない。
知恵と統率こそ、戦いの要諦だと。
後の世代になるほど、
策もなく突っ込む犬が増えたのは、
その教育者が不在だったからだ。
じっ様という、“基盤”が抜け落ちた。
軍の形は残っても、
軍の哲学が消えた。
彼は「英雄の育成者」だった
彼は愛を語らない。
抱きしめもしない。
笑顔もない。
けれど、
犬たちが死なない方法を選んだ。
戦場の現実を知り、
弱さの先にある死を知り、
牙だけでは守れない世界を知り尽くしていた。
だから、人は誤解する。
犬も恐れた。
読者も嫌った。
でも本当は、誰より犬を信じていた。
そしてあの戦いの結末が示した。
じっ様の厳しさは、
犬を傷つけるためではなく、
犬を生かすための厳しさだった。
ならば、もう呼び方を変えよう。
彼こそが、
“英雄の育成者”
だったと。
第1回 結び

次回は、じっ様の「残酷さ」がどこから始まったのか──
物語が始まるより前、あの夜の栗駒山にさかのぼっていく。
夜の栗駒山。
死傷者を出し、猟師仲間からのSOSを受けて、
じっ様は熊犬シロと、数匹の犬たちを連れて山に入る。
あたり一面、赤カブトの爪牙でやられた遺体。
雪にしみ込んだ血の匂いが、冷たい空気に立ちこめている。
生き残っているのは、
白い息を吐きながら銃を構えるじっ様と、
その横に立つシロと、まだ幼いリキだけ。
他の仲間は、猟師も含め、みな、赤カブトの爪牙に倒れていた。
じっ様の左耳は、赤カブトにそぎ落とされていた。
それでも、シロが身を張って作った一瞬の隙を逃さず放った弾丸は
赤カブトの右目を貫き、脳髄まで達する。
──それでも、死ななかった。
怒りに狂った赤カブトは暴れ、
シロをくわえたまま谷へ転げ落ちていく。
リキの知らせで、じっ様は、なんとか一命をとりとめた。
その夜から、山は変わった。
季節が巡っても、雪が積もっても、
あの夜の匂いだけは消えない。
それは、五兵衛だけが知っている「世界の変化」だった。
そして、五兵衛だけが、その意味を理解していた。
偏屈者では終わらせない。
正しく語りなおすために、
この連載は始まる。
「英雄を育てた人」として描きなおすために、この連載は続く。
次回はこちら👇️
『熊撃ち老人伝説』第2回 ─ 『銀牙-流れ星銀-』じっ様再評価論 栗駒山で始まった「犬殺し」と英雄育成の原点
-

-
『銀牙−流れ星銀−』じっ様はなぜ“残酷”だったのか?|栗駒山の惨劇と“決断の理由”を解説
続きを見る
じっ様と赤カブトの“最初の夜”。
氷点下の雪山、銃声、そして運命が始まる一冊はこちら。
──────
引用・参考文献