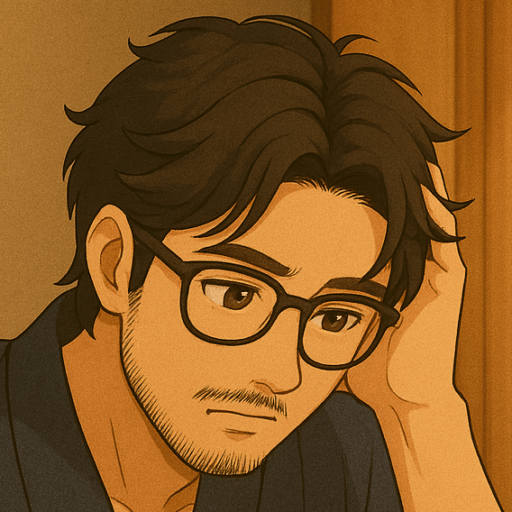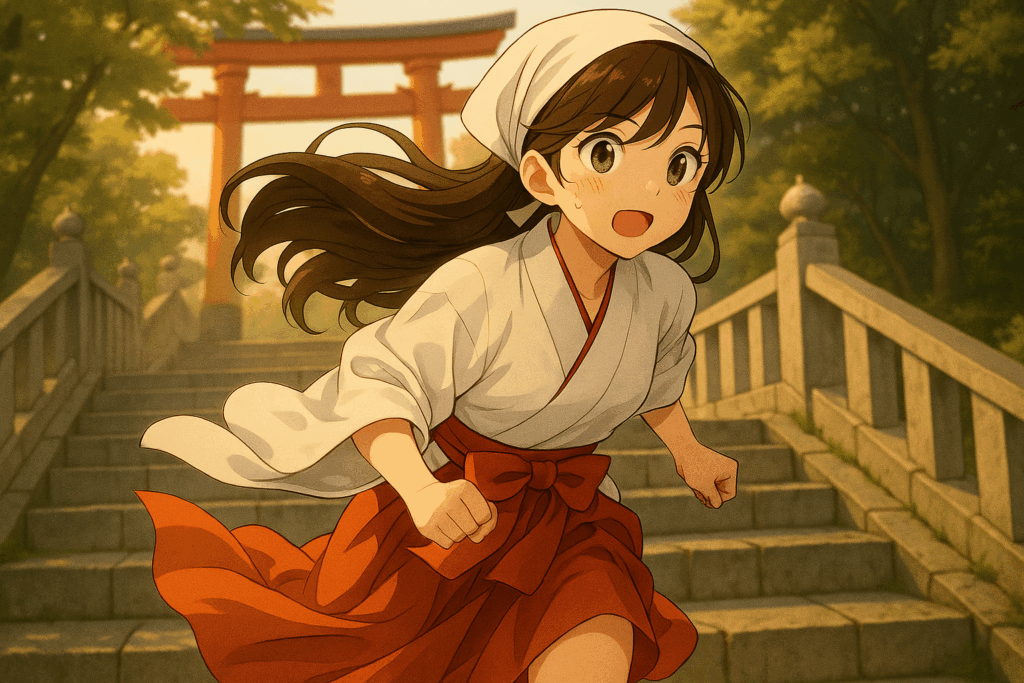
明日は、再開の日。
待ちきれなかったの──逢いたくて、走り出した秋
神社の石段に舞う紅葉と白装束。
恋に染まった風花が、胸を焦がして駆け出す。
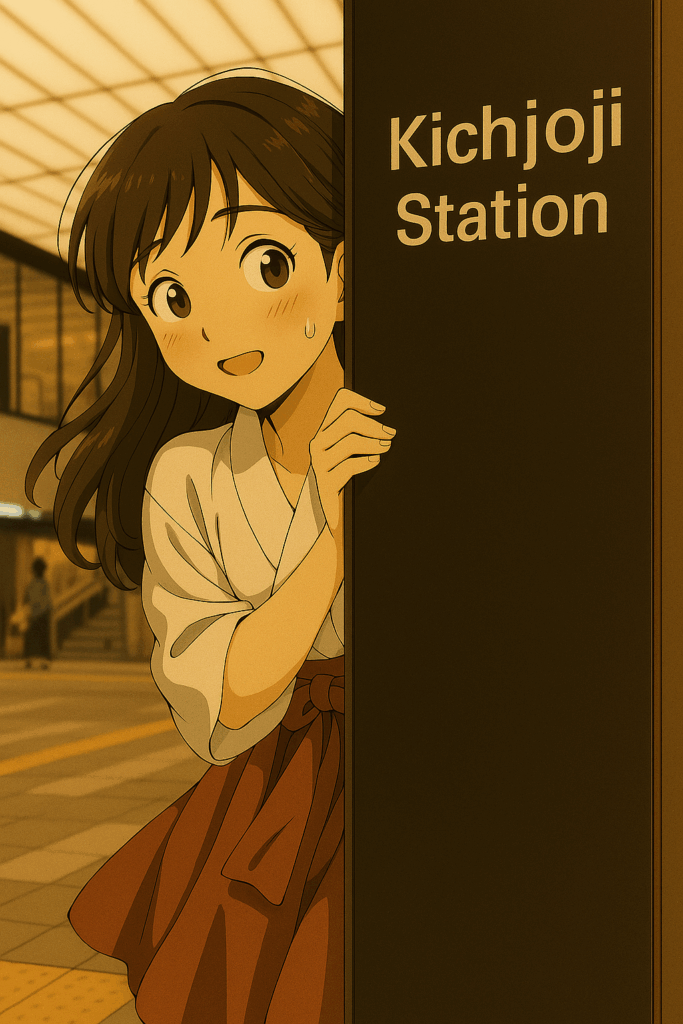
神社の休憩時間に、下見のために、そっと駅まで抜け出してきた風花。
彼の姿を見つけたその瞬間──胸がとくんと高鳴った。

吉祥寺駅に到着。
けれど、これから会う彼女は、まだ知らない。
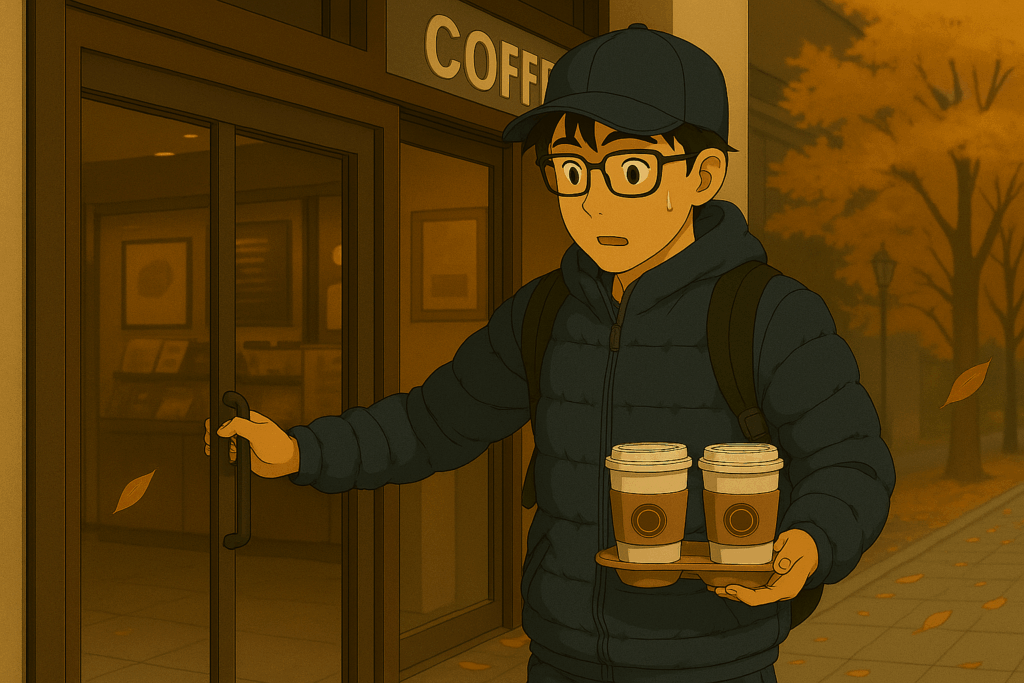
コーヒーは、ふたりぶん。
いっしょに飲めたらいいなって、思って……。
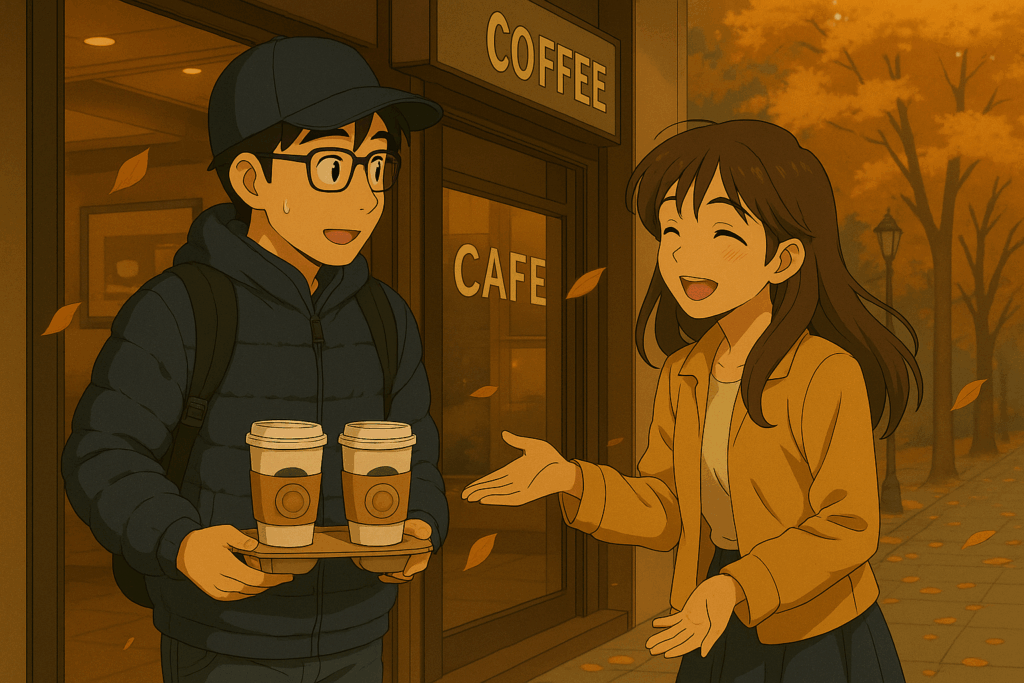
「……わたしも、もつよ?」
すっと差し出されたその手に、秋の風がふわりと吹いた。
落ち葉がカサコソ鳴るたびに、ふたりの靴音が、寄り添って響いた。
井の頭公園の池のほとり──
肩を並べて歩く秋の午後。
彼は、風花の右側にいて、
ポケットに入れていた焼き芋をふたつ取り出す。
「ほら、あったかいうちに食べよ」
ベンチに腰を下ろすと、ほわりと甘い香りが立ちのぼる。
秋の空気に、やさしくとけるように。
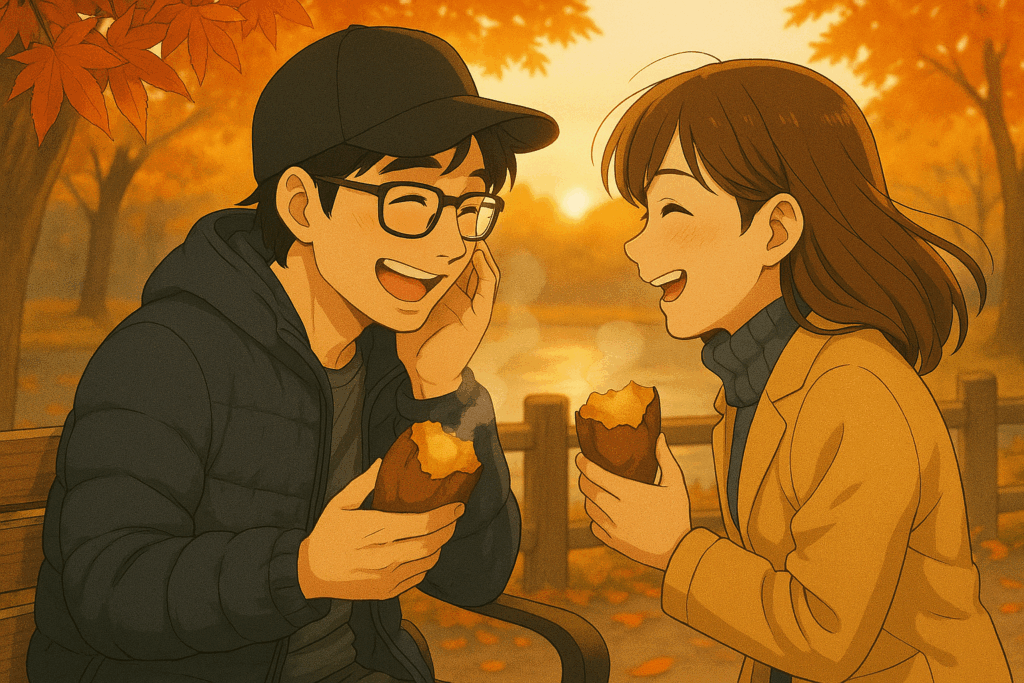
「さっき、“あちっ”って言ってたもん」
「えっ!? 見てたの……?」
恥ずかしさとぬくもりが、ひとつになった。
「ふぅ……あちっ」
彼が指先をふっている横で、
風花が一口かじる──
「んふふ……あちぃっ!」
ふたり、顔を見合わせて笑った。
笑い声が、風にのって舞いあがる。
その時。
「──あっ、あそこ見て!」
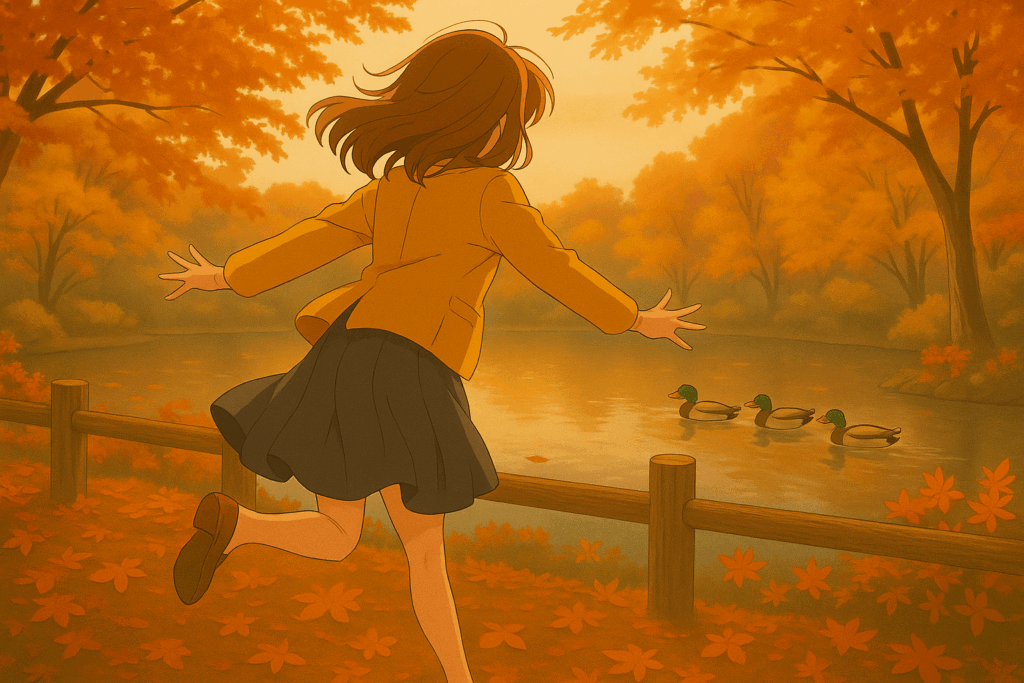
あっ、あそこ見て──突然立ちあがって、池の方へ小さく駆け出した。
スカートのすそが、紅葉の風にひらりと踊る。
「カモさんたち、ぐるぐる回ってる〜!かわいすぎっ」
彼が立ちあがると、風花はくるりと振り返って、
いたずらっ子みたいに手招きする。
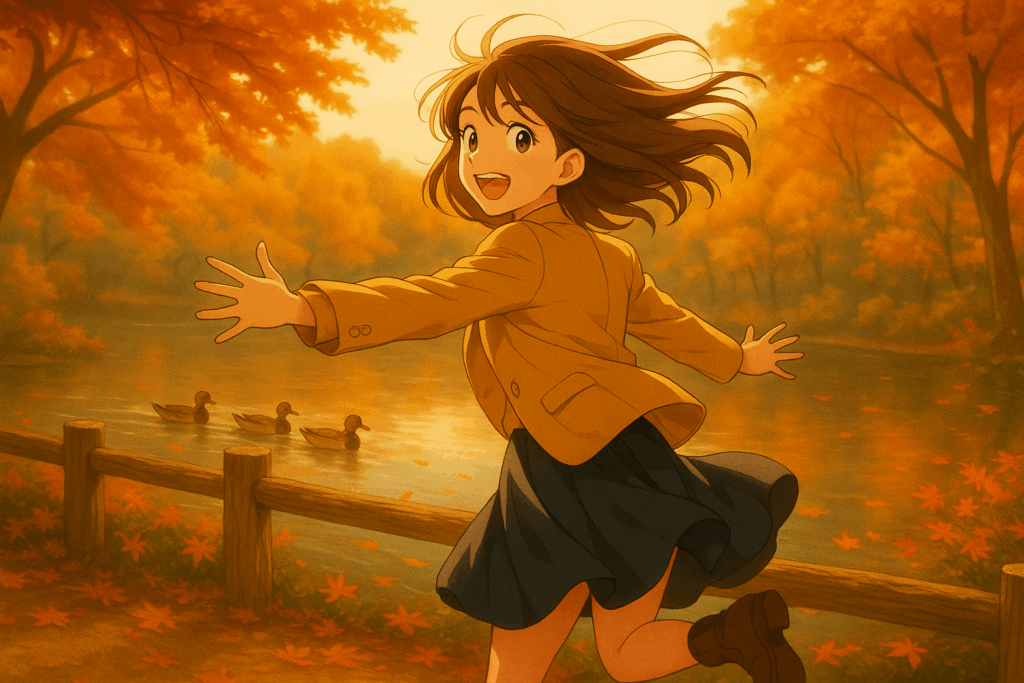
「ほら、早く〜っ!」
その声が、秋の空に跳ねた。
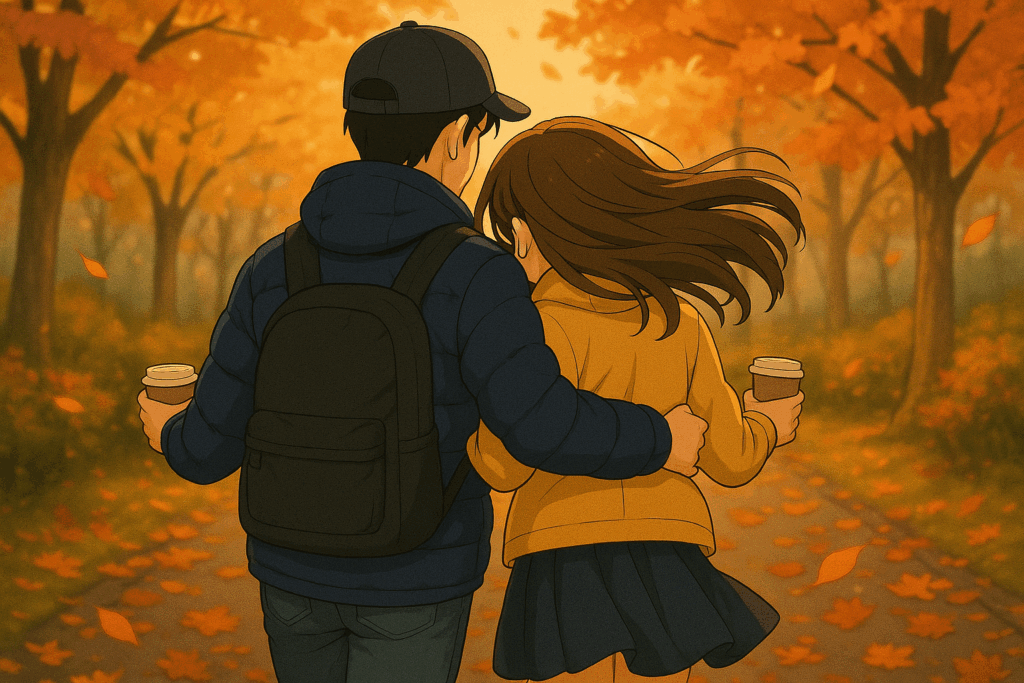
寄り道ばかりの午後だった。
それが、ふたりにはちょうどよかった。
まるで、季節の魔法に連れ去られるように──
ふたりはまた、並んで歩き出した。
寄り道ばかりの、秋の午後。
でも、それが、いちばんたのしい時間だった。