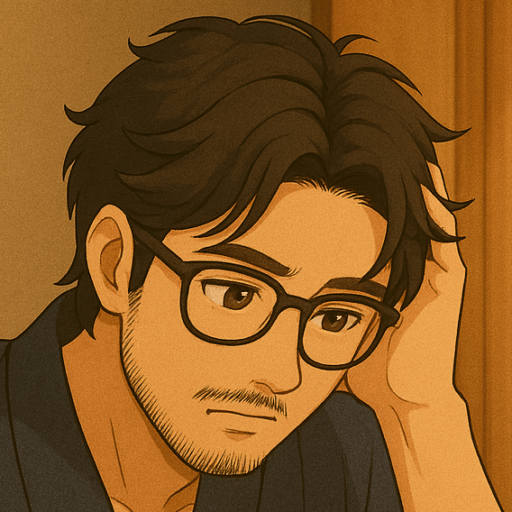はじめに──美談の影にある「構造のゆがみ」
『相棒24』第16話「町一番の嫌われ者」。
見終わった瞬間、胸の奥がざわついた。
それは、物語が悲しいからではなく
──支援の世界で最も危険な“ある構造”が、
美談として処理されていたからだ。
多くの視聴者は、青年・菊川の誠実さや、
右京のやさしい言葉に胸を打たれたようだ。
ラストは柔らかいBGMと、特命係の微笑み。
ニュースでは
「杉下右京、相棒24で見せた優しい言葉が心に響き、視聴者の共感を呼んでいる」
として美談的に扱われていた。
しかし、
当事者学の視点で読みなおすと、
このエピソードはまったく違う表情を見せる。
今回の物語が扱ったのは
「優しさ」の話ではなく、
支援者が無自覚に人を傷つける構造そのものだからだ。
象徴物(えんむすび)と境界線──見落とされた危険性
この回は、
社会から孤立し、心の均衡を失い、
ゴミを集めながら町をさまよう55歳の女性、
そして支援職の介入ミスによって
引き起こされた死を扱っている点で、
きわめて現代的なテーマを含んでいた。
問題の中心は、市役所職員の菊川が
佐藤さんに渡した「えんむすび」のお守りだ。
彼はこう言った。
「深い意味はなかったんですが……」
ところが、支援の世界では
“深い意味はない行為”ほど危険なものはない。
なぜなら、
支援者と当事者には
圧倒的な非対称性 があるからだ。
支援者の軽い一言、軽い贈り物は、
当事者にとっては“決定的な意味”として受け取られる。
今回のお守りは、
- 佐藤さんが初恋で裏切られた詐欺師(山川)と同じ形
- 同じ色
- 表記すら「えんむすび」で一致
という最悪の条件が揃っていた。
転移と再演──佐藤さんの心に何が起きていたのか
佐藤さんがそのお守りを受け取った瞬間、
目が一気に“うるんだ”のを覚えているだろうか。
あれは、ただの“勘違い”ではない。
心理学的には、
- 恋愛転移(love transference)
- トラウマ再演(re-enactment)
- 対象の同一視
が一気に起きた瞬間だ。
過去の初恋(山川)
↓
同じ象徴物
↓
似た雰囲気の青年(菊川)
↓
「また愛してもらえるかもしれない」という錯覚
過去に佐藤さんを破滅させた初恋の詐欺師・山川と、
菊川は外見的特徴から優しさの質、象徴物(えんむすび)に至るまで、
複数のポイントで“深い類似性”として結びついてしまっている。
そのため佐藤さんの心は、
現在の人物を過去の加害者へと重ね、
境界線が融解していく──これは“誤解”ではなく、
トラウマ再演の極めて典型的な心理現象である。
しかし作品は、この重大な兆候を説明しないまま放置した。
これこそが今回の脚本の最大の欠落である。
「ときどき、ぼくのことを山川さんと呼んで」
──転移のレッドシグナル
菊川は言う。
「ときどき、ぼくのことを山川さんと呼ぶようになって。
誰のことを言ってるのか全然わからないんですけど」
これは最も危険な兆候だ。
支援者本人が自覚していないうちに、
当事者の心の中で
菊川 ⇄ 山川
が接続されてしまったのだ。
境界線は、すでに崩壊していた。
筆者の背景──なぜこの問題に敏感なのか
ぼくは、当事者としても支援者としても、
長い時間をかけて
「人がどのように壊れ、どのように立ち直るのか」
を見つめてきた人間だ。
精神科医や臨床心理士との対話の中で、
ぼくは“安全に人と向き合うとは何か”を身体で覚えた。
なぜか。
境界線が守られなかった瞬間が、
ぼくの人生を大きく歪めてしまった経験があるからだ。
支援される側の痛みも、
支援する側の責任の重さも知っている。
優しい声かけがどれほど人を救うか。
無自覚な一言がどれほど人を壊すか。
ぼくは、その両方を知ってしまった。
だから今回のエピソードで、
支援職では明確に禁忌とされる「境界侵犯(boundary violation)」が
“スルーされてしまった”ことに、
強烈なざわつきを覚えたのだ。
これは「誤解した当事者の悲劇」ではない。
支援者が境界線を引けなかった悲劇である。
しかし脚本は、この核心部分に触れない。
むしろ“優しい言葉”で包み込み、
美談として処理してしまう。
だが、
支援の現場ではこうした軽率さは、
本当に人を死なせることがある。
善意は免罪符ではない。

「ぼくは、どうすればよかったのか」──支援者の問い
菊川のこの言葉は、支援職が必ず通る分岐点。
「ぼくは、どうすればよかったのか」
ここは本来、
作品が最も時間をかけて取り扱うべき場面だ。
しかし右京は、こう返す。
「あなたは、やるべきことを十分やったんじゃありませんか」
これは、本来の右京の本質から著しく乖離している。
杉下右京はシリーズを通じて、
制度的暴力・支援ミス・行政の構造的欠陥に対して
最も鋭い批判を向けてきた存在である。
彼の倫理観は
「善意であっても結果が人を傷つければ、それは検証されなければならない」
という理念に基づく。
今回のセリフは、この右京像を根本から損なっている。
善意と影響力は別問題。
意図と結果は別問題。
境界線の逸脱は“善意でも”起きる。
そこを語らず「十分やった」で締めてしまうのは、
支援の世界ではもっとも避けるべき言葉である。
献花とエンディングが覆い隠したもの
ラスト、菊川は佐藤さんの死亡地点に献花を置く。
これは哀悼であると同時に、
“説明のつかない罪責” の反映でもある。
エンディング。柔らかいBGMが流れる。
一見すると、特命係らしい“人間味の余韻”のはずだ。
しかし今回のそれは、むしろ痛みを強調してしまう。
佐藤さんの死の背景にあった構造的問題──
境界線の逸脱、象徴物の危険性、トラウマ再演、
そして支援者の影響力の非対称性──
これらはどれも語られないまま、
音楽だけが“温かい物語”を提示して終わってしまう。
音の優しさと、物語の残酷さ。
その齟齬こそが、
今回のエピソードの本質的な違和感である。
その状態で、
右京と薫は優しい微笑みで彼を見送る。
これは、
“語られるべき痛みを美談で蓋をした”
ような終わり方だ。
結論──描かれなかった“支援の現実”
ぼくがこのエピソードに強い違和感を覚えたのは、
単に脚本の整合性の問題ではない。
人が壊れる瞬間を見てきた目で見たとき、
描くべき現実が描かれていなかったからだ。
今回の問題は、
「勘違いした当事者」
ではない。
「境界線を引けなかった支援者」
の側にある。
そして作品は、それを“美談”として処理してしまった。
支援の現場で最も注意が必要なのは、
支援者の善意が、無自覚に人を傷つける構造 だ。
今回の相棒は、
その核心を描かなかった。
だからこそ、
ぼくは書かなくてはいけなかったのだ。
支援とは、優しさではなく
「境界線を守る勇気」である。
──その事実を、
ぼくらはもっと静かに語っていく必要がある。

傷ついた誰かを想うこと。支援という行為の重さに向き合うこと。
壊れやすい心を前に、人はどんな距離で立つべきなのか──。
その全部を、この静かな風景がそっと受けとめてくれているような、そんな余韻だけが残っている。
ぼくは今日も、その風に耳を澄ませながら、書き続けていこうと思う。
📚相棒を小説版でじっくり楽しみたい人へ
📚 相棒 season23 ノベライズ(朝日文庫)
上巻には「警察官A」こと高田創くんの交番配属エピソードも収録!
小説ならではの心理描写が深くて、読後の余韻がしみるよ。
📦
上巻・中巻に加えて、下巻 12月5日発売中✍️