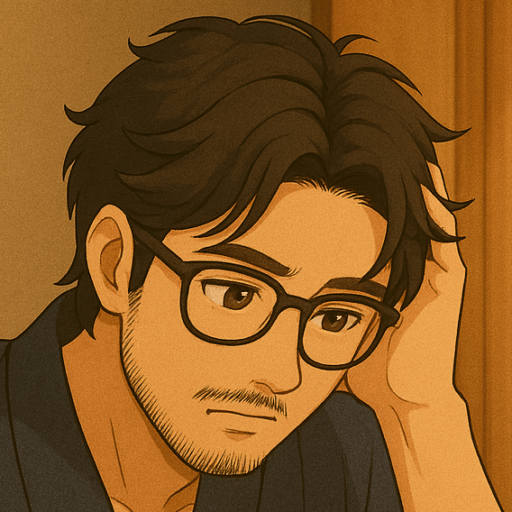子どもの迎えに行けないくらい研究が大事かって聞いているんだ !
出典:映画『ドラゴンボール超スーパーヒーロー』/バード・スタジオ/集英社/東映アニメーション
ピッコロが、孫悟飯に説教している場面だ。ひとり娘であるパンちゃん(3歳)の保育園のお迎えに行けないことにだ。

パンちゃん、モザイク付きで登場(また、レッドリボン軍に誘拐されてもいけないので、ビーデルさんからお達しが)
映画『ドラゴンボール超スーパーヒーロー』修業中のひととき。パンちゃんが満面の笑みで「ヒヒッ」と、ミネラルウォーターをピッコロさんに手渡すシーン。あまりの可愛さに、私が全面降伏したのは、ココだけの話だ。
ああ、いえ…でも、ピッコロさんが、行ってくれるんでしょ?
出典:映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』/バード・スタジオ/集英社/東映アニメーション
話は戻り、ピッコロさんのお説教に対する孫悟飯の返事は「いつものようにお願いしますよ」と。内心まんざらではなさそうな、ピッコロさん。もはや“保育士ピッコロおじさん”を家族の一員として信頼(行ける人が迎えに行くという)していることが伺える。
事実、鳥山明先生は「悟飯一家に対してピッコロは、どのような存在だと思いますか?」という質問に対して、以下のようにコメントされている。
悟飯は幼少期をピッコロと共に過ごし修業を受けてきた関係で、ずっと強い絆で結ばれてきました。そして、ビーデルやパンも、ピッコロは誰よりも頼りになり信頼の置ける家族の一員のように思っているのです。
出典:映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』公式サイト
と、コメントしていますが、ここでいう「誰よりも」の中に、我らが孫悟空(戦闘以外)は含まれていない模様(笑)
シャイな、鳥山明先生、モザイクをかけてもらって登場。冷や汗をかいている・・・

ピッコロは、孫悟空の抹殺を宿命付けられた悪の化身
かつてのピッコロの姿を観ていた頃の自分には、将来(現在)の姿というのは、到底、想像つかないだろう。なぜなら、ピッコロは、世界を震撼させた、あの「ピッコロ大魔王(神様の悪の心が分離した存在)」が、死ぬ直前に産み落とした子だ。
その父は、今際の際に「わが子よ…我が子よ いつか父の恨みをはらしてくれ……!」と言い遺す。そして、ピッコロの初登場時のセリフは「父のカタキ殺す!」だった。生まれながらにして、敵討ち(孫悟空の抹殺)を宿命付けられた悪の化身。
人生が動き出す”孫悟飯"との出逢い
「恨むんならてめえの運命を恨むんだな⋯このオレのように⋯⋯」
出典:漫画『ドラゴンボール完全版』 第14巻/鳥山明・バード・スタジオ/集英社
きっかけはどうあれ、父の宿敵たる孫悟空との共闘にならざるを得なかったピッコロは、来たるべき、サイヤ人の地球襲来に備え、孫悟飯を鍛えるときに放ったセリフだ。しかし、このセリフの趣旨をおもんばかると、悪の化身としての自分自身を、肯定しているわけではないことが分かる。
そして、ナッパの攻撃から、孫悟飯を全身でかばい、今際の際のセリフがこれだ。
「悟飯⋯⋯オ⋯オレと⋯ま⋯まともにしゃべってくれたのは⋯おまえだけだった⋯⋯」
出典:漫画『ドラゴンボール完全版』第15巻/鳥山明・バード・スタジオ/集英社
天下一武道会で自らを「マジュニア」と名乗って出場した”孤高”のピッコロ。
ピッコロは”孤高”ではあったが、無意識レベルでは“孤独”であったかもしれない。幼少時に通りがかった、子どもの誕生祝をしていた一家団欒の様子に我慢ならなかったか、羨ましかったのか、ケーキを滅茶苦茶にしたり、子どものおもちゃを壊したりと、余りにも自分の境遇との違いに言い表せる言葉を持っていなかったシーンは印象的であり、胸が痛んだ。“アニメ『ドラゴンボール第124話:雲の上の神殿』”
古代ギリシアの哲学者アリストテレスいわく、「人間は社会的動物」であるが、生まれながらに忌み嫌われた存在として、生きてきた彼の寂しさ。涙ながらに吐露するピッコロだったが、無邪気な孫悟飯と交流することで「人としての心」を知ることになる。
「悟飯ちゃんも悟空さもピッコロさも気いつけてな」
ベジータを地球から追い払い(事実は、孫悟空が死にそうになっているベジータのことを”もったいねぇ(出典:漫画『ドラゴンボール完全版第17巻 其乃二百四十一孫悟空の頼み⋯/鳥山明・バード・スタジオ/集英社)』“と見逃したのだが、これは内緒だ)、生き残ったZ戦士達。界王様のもたらした情報により、ナメック星のドラゴンボールで、サイヤ人との闘いで死んでいった仲間達を生き返らせることができる可能性を示唆される。
ナメック星へ行くメンバーを決めるとき。「ボ⋯ボクも つれていってください⋯! ぜひ⋯」「ピッコロさんを⋯この手でいきかえらせてあげたいの⋯⋯」と訴える孫悟飯に対し、チチは「ピッコロなんてカンケイねえべっ!!」「おめえはちいさなコドモだ!!コドモはコドモらしくしてりゃええっ!!」と。
チチの振る舞いは母親として当然のものだ。ピッコロは息子をさらった憎い相手に他ならない。なにせ、”誘拐”し、獰猛なティラノサウルスが跋扈する荒野に放置し、修業という名の拷問をした張本人だからだ。孫悟飯はわずか4歳。歴戦のZ戦士達でさえも、全く刃が立たなかった死戦場に駆り出すなど、もはや狂気の沙汰以外のナニモノでもない。

孫悟飯は、自ら設計図を書き、帆付きイカダを製作。そして無人島から一時的離脱(逃げ出したわけではない。母親に会ったら戻ってくるつもりと言っている)に成功する(出典: アニメ『ドラゴンボールZ 第15話:ピッコロからの脱出! 嵐を呼ぶ悟飯』)
そして、続く『ドラゴンボールZ 第16話:走れ悟飯! チチの待つなつかしのパオズ山』”では、我が家を間近にしても、戻ることはしなかった孫悟飯。引き返す道すがら、ピッコロから「お前の使命はなんだ。言ってみろ!」と問われ、力強く「サイヤ人を倒し、地球を救うこと!」と応えた姿は、6か月前の”泣き虫”悟飯ちゃんのそれではなく、Z戦士となっていた。

ときはさらに進んで、人造人間編。
孫悟空の提案とはいえ、孫家で、孫悟飯、ピッコロと3人で、人造人間が現れる3年間を過ごすことになる。ピッコロは、水だけで生きていられる生命体。だが、孫悟空いわく、“チチの飯が一番うまい”という、親子3人が、食卓を囲む様子を見ながら、どこかのタイミングで、ピッコロも、この輪に加わった可能性が高い。
アニメ『ドラゴンボールZ 第125話 免許皆伝? 悟空の新たなる試練』を観るまでもなく、孫悟空はもとより、ピッコロでさえも、チチに逆らうことなど出来やしないと想像するに容易い。ひょっとしたら、孫悟飯の勉強の手伝いだってしたかもしれない。家事や掃除。その他もろもろ。食事に、寝る場所の提供を受けたピッコロが拒否できるわけない。
ゆえに、おそらく、この3年の間で、チチのピッコロ観が、大きく変化した可能性は極めて高い。真面目でストイック。武道、そして勉強を極めるために共通する要素だ。模範的な存在とまでは思い至らなかったとしても、「悟飯ちゃんが懐くのは当然だな」と。
この時点でのピッコロは、ナメック星で、ネイルと同化を果たした姿だ。ネイルは最長老様に仕える任務に忠実な存在であり、礼儀礼節をわきまえているだろう。すなわち、彼は、すでに「ピッコロ大魔王」とは別次元の存在といってよい。
後に、ピッコロが、神様と融合し、さらに”人格者である神コロ様“となったが、すでに、この時期でも、人格者になりつつあったと考えるほうが自然だ。だからこそ、人造人間との闘いに赴くZ戦士に対し、「悟飯ちゃんも悟空さも”ピッコロさ”も気いつけてな」となるわけだ。ピッコロは、ついに、チチにさえも、受け入れられたのだ。
誰もが“安全基地(挑戦や不安と向き合うための“心の母港”)”を必要とする

CBT(認知行動療法)※では、自分の感情を支えてくれる“安全基地(挑戦や不安と向き合うための“心の母港”)” を持つことが、心の回復に大きく貢献すると考えられている。それは、ピッコロにとって孫悟飯が。パンちゃん(映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』)にとって、ピッコロが。──これは、まさに『お互いにとっての安全基地』の物語だったのだろう。”お互いにとって”・・・心理学ではこれを”安定した応答性(Responsive)”と呼ぶが、安全基地として機能するには、この”安定した応答性”と、”過度にコントロールしない姿勢”が重要と言われている。ピッコロは、まさにこのバランスを、孫悟飯とパンちゃんに対して絶妙に保っている。
※ CBT(認知行動療法)とは、思考や行動のクセに気づき、心のバランスを取り戻す心理療法のこと
また、CBT(認知行動療法)の考え方では “自動思考”──つまり湧き上がる感情や思い込みをそのままにせず、『違う見方』を探す作業がとても大切だ。これを、CBTでは、「自動思考を観察する目=メタ認知的視線」というが、「ある出来事に対して、自分の中でパッと浮かぶ“反応”を一歩引いて見つめる目」のこと。たとえば、ピッコロが孫悟飯との出会いを通じて、自らの“生まれ持った宿命”に新たな意味(平和なときは、パンちゃんを育てる指導者&保育士。有事には、チームをまとめる作戦参謀&司令塔として)を見出していった姿は、心の成長のモデルケースといっても過言ではないだろう。
ピッコロさんと孫悟飯、そしてパンちゃん。CBT(認知行動療法)では、「人は誰しも、感情を支えてくれる存在=“安全基地”を必要とする」と考える。ピッコロさんにとって孫悟飯は、自分を変えてくれた存在。パンちゃんにとってピッコロおじさんは、何気ない日常の中で寄り添ってくれる“特別な誰か”だったんだ。
誰かを安全基地と感じること。自分が誰かの安全基地になれること。その「双方向性」は、自己肯定感と安心感を育てる、大きな原動力となる。この関係性は、CBTでも大切にされる考え方だ。
「オレとまともに喋ってくれたのは、お前だけだった」というセリフは、かつての孤独と、心の扉を開いた体験を象徴している。それが、今のパンちゃんへの優しさ、献身へと引き継がれている。パンちゃんを“守ることで、自分自身が救われる存在”=ピッコロの心の支えに他ならない。
ドラゴンボールは「ギャグ漫画の皮をかぶった哲学書」なのだ。