
──「やっぱり、自分は、“法”に関わっていたい」
大学時代、1年目は会社法を履修していた。けれど、どうにも興味が持てなかった。2年から専攻を変えて、家族法を選んだとき──初めて、法学というものの面白さに触れた。結婚、離婚、相続、親子関係──人と人とのつながりの中で生じる問題を、法というフィルターを通して読み解くことが、とてもリアルに感じられた。
教授は、ヨーロッパのとある国で教鞭をとっていた経験を持つ方で、ゼミでは日本と海外の文化の違いに触れることも多く、日本では“当たり前”とされる価値観が、他国では全く違うかたちを取っていることに、目からウロコが落ちるような驚きがあったことを覚えている。今でいう“多様性”なのだろう。
印象的だったのは、模擬裁判。ゼミ生同士で原告と被告に分かれて、実際の判例をもとに議論した。もともと負け戦だった。が、なんとか論理を組み立てて勝てないかと、当時、大学の判例室にこもって、原告側として“どうやったら勝てるか”を考え続けた。天井まで届きそうな判例集に埋もれながら、勝ち目が薄いことは分かっていたけど、それでもあきらめたくなかった。
結果は、敗訴。けれど、教授が言ってくれた「よく調べたな。」の一言は、今でも忘れない。この頃から、漠然と「将来、法律に携わる仕事がしたい」そんな気持ちが芽生え始めていた。
一度は、民間企業に就職し、人見知りも克服し、吃音にも折り合いをつけられた。でも、心のどこかでずっと感じていたのは、
「このままでいいのかな」と。結局、会社を辞めて、再び“法”の世界を目指すことにした。資格は、家族法を活かせる分野に決めた。
そして、いよいよ始まる「開業」の日々。──そこに待っていたのは、想像以上に深い“個人”との関わり。
-
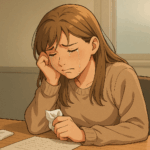
-
第4章『開業──“法制度”ではなく、“人”をみる仕事へ』
続きを見る