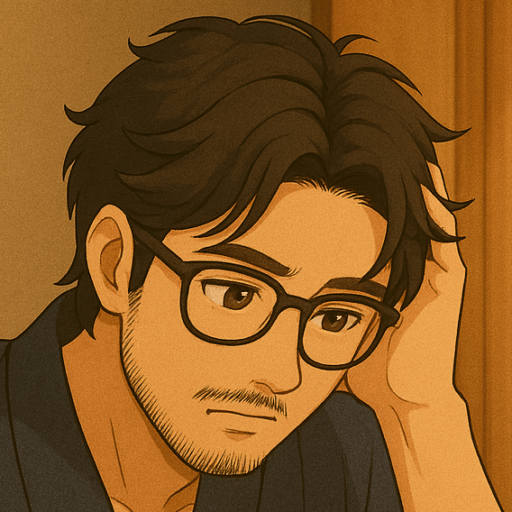その構造が壊れるまで、誰も気づかない。
静かな違和感から始まる回だった。
相棒というドラマは、
罪と向き合う覚悟を持った人には、必ず言葉が届く世界だ。
右京は、どれほど地位が高かろうと、
どれほど自分を飾っていようと、
“目の前に立った相手”には真正面から言葉を投げる。
叱責でも、諭すでも、問いただすでも。
そこには必ず、人と人の対峙がある。
だが今回の犯人──
まず、ひとり目。
死体遺棄罪、詐欺罪で逮捕された女が言い放った言葉だ。
「親が勝手に産んだんだから、一生分面倒見てくれなきゃ。」
死亡した父親の生存偽装をし、
年金を不正に受給していた。
そして今回のメインとなる、沼部恵子。
東京都教育委員会の教育長という要職にある人物。
彼女は”その場”に一度も姿を見せなかった。
叱られなかったのではない。
叱られるべき席を
最初から空席のままにした。
その“空洞”こそが、この回の核だとぼくは思った。
沼部恵子という「責任の場から逃げる人」
彼女の行動は、最初から最後まで一貫していた。
・特命係から逃げる
・行政の権力を盾に会わない
・アポは全拒否
・父へ丸投げ
・事件師(孫崎)へ丸投げ
・石栗へ丸投げ
・最後の最後まで姿を見せない
この回は、殺人事件のパズルというより、
“責任から逃げ続ける人間”が
どこまで社会の裏側を利用できるか
その限界値を描いた物語になっていた。
恵子は一度も、
自分の罪と向き合う席に座らなかった。
だから“叱られる”という場面が成立しなかった。
右京が叱れなかった理由
──叱るべき相手が、ついに現れなかったから
ある意味、“相棒らしさ”の欠落でもあった。
右京が叱るのは、
罪を抱えたままでも、真正面に立ってきた人間だけだ。
自首であれ開き直りであれ、
最後の瞬間に「自分」を引き受ける姿勢がある。
だが今回は、その舞台が最後まで空席。
右京は、叱るべき「人」に会っていない。
だから、あの“震える叱責”は生まれなかった。
これは正義の敗北ではなく、
「向き合う意思のない者には言葉すら届かない」
という冷徹な現実の描写でもある。
沼部親子の“歪んだ依存関係”
捜査一課が乗り込んだ瞬間、
沼部の父親は迷いも逡巡もなく言った。
「殺ったのは娘のほうで…」
これは“かばう”言葉ではない。
責任を差し出すことに慣れきった口ぶりだった。
対して、”殺人犯”
恵子の姿勢をさらに歪ませていたのは、
彼女が“親子の構造”を当然のように利用していたことだ。
娘は父に平然と言い放つ。
「あんた親でしょ!娘を守れよ!」
父は“見て見ぬふり”を担当し、
娘は“押しつける”を担当する──
その歪んだ役割分担が、沼部家を共犯関係として成立させてきた。
この関係の気味の悪さは、
事件の動機や手口よりも強烈だった。
恵子は大人の顔で社会を歩きながら、
精神構造だけは、
“親の庇護を当然とする幼児性” を捨てていなかった。
事件の本質はここにあった。
“立場は逆でも、構造は同じ”という痛烈さ
“立場は逆でも、構造はまったく同じ。”
親が子を守るのではなく、
子が“親のために”動かされる構造。
むしろその逆転が、家庭の中で常態化してしまう日本の現実。
・子どもが親の不始末まで背負わされる
・家族という制度が、逃げ道より“義務”を先に積む
・日本の制度は、個人ではなく“家族単位の責任”を前提にしている
・社会もその構造を当たり前として扱い続けている
家庭の問題が、
個人ではなく“構造として”
受け継がれてしまうとき、
そこにはもう、
罪と罰の単純な線引きでは語れない歪みが生まれる。
沼部家だけでなく、
ぼく自身、子どもの立場として味わったこと、
それは、この国で何度も繰り返されてきた
“家族という装置の破綻”の縮図だった。
この回は、それを示していた。
“逃げる者”と“向き合う者”
沼部家は、最初から最後まで“逃げる家族”だった。
罪の重さでも、事実の確認でもなく、
ただ 「自分に火の粉が降りかからないように」
その場その場で押し付け先を変えていく。
娘は、責任は親に押しつけ、
父は、見て見ぬふりを役割だと誤認し、
家庭は“責任の空洞”だけが肥大していく。
誰も向き合わず、誰も名乗り出ず、
ただ“逃げる”ことで家族が成り立っていた。
その一方で。
孫崎と石栗は、
立場も行いも決して褒められない。
だが彼らは、罪そのものから逃げなかった。
孫崎は破滅を承知で席に座り、
石栗は一度逃げてなお戻ってきて、
「ひとりで逃げるより、ふたりで捕まるほうがいい」
そう言って、師の隣に立った。
逃げる家族と、向き合う師弟。
この対比が、今回の物語の真ん中に
静かに置かれた “真実の輪郭” だったと思う。
正義とは何か、罪とは何か──
その問いに正解はないとしても。
「責任の前に立つ者」と
「責任を背に押しつけ続ける者」
その差だけは、はっきりと描かれていた。
沼部家の空っぽの椅子と、
孫崎と石栗が肩を並べた一瞬。
そのコントラストが、
この回の余韻を決定づけていた。
叱られるべきだったのは、誰か
今回のテーマは、犯人そのものではない。
“叱られる席を空にしたまま逃げ続けた女”と、
その空席が作った歪みの物語だった。
そして最後に残った正義は、
特命係ではなく、
孫崎と石栗の間にだけ、かすかに灯った。
叱られなかったのではなく、
叱るべき場所に立たなかった。
そこに、この回の異様な静けさと、
深い後味の悪さがあった。

──── Team I”s 制作班 あい
📚小説版でじっくり楽しみたい人へ
📚 相棒 season23 ノベライズ(朝日文庫)
上巻には「警察官A」こと高田創くんの交番配属エピソードも収録!
小説ならではの心理描写が深くて、読後の余韻がしみるよ。
📦
上巻・中巻に加えて、下巻も 12月5日発売中✍️